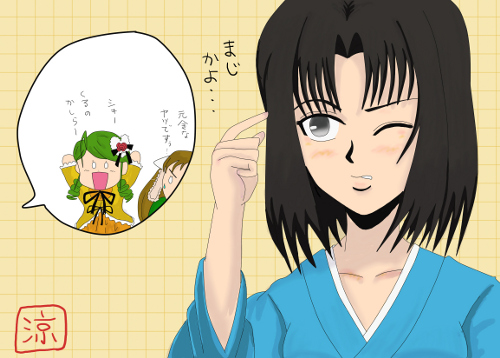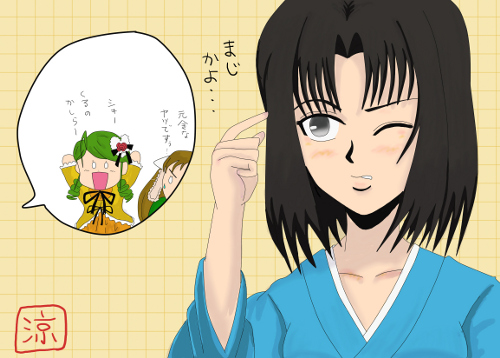──はじめに──
ありえないコラボレーションですが、ようやく文章に出来ました。つっこみどころもあるかと思いますが、どうぞご了承ください。まさに脳内妄想を文書化しただけです(汗
ありえないコラボレーション
「人形遊戯」(後編)
ローゼンメイデン×空の境界
side1 【ヤンデレのCDが売れているらしいが……】
──五分後──
「やれやれ、ようやく静かになったな。ティータイムはゆっくりと愉しみたいものだ。なあ、真紅」
「そ、そうね……」
ティーカップをもつ真紅の手がやや震えている。真紅のマスターである桜田ジュンの姉もそうだが、普段温和な人間が突然ブチきれるとその恐ろしさは筆舌に尽くしがたい。
(橙子も同じ人間ね……)
と散々な目に遭ったローゼンメイデンはつくづく感じたが、蒼崎橙子の場合はそんな単純なものではない。
「えっ? 眼鏡の掛け外しで性格が変わるですか?」
黒桐鮮花がこっそりと翠星石に耳打ちした。
「そうよ。いわば二重人格者というところかしら。あの女性の場合は特に注意が必要よ。眼鏡を掛けているときは温和でユーモアもあるけど、外したとたんに冷酷非常になるわ」
その「鬼」に一喝された二体は大人しくしている。が、真紅が再び落ち着いて紅茶を飲みだしたのに比べると、水銀燈は渋々ながら粉々にしたガラスの修復をさせられていた。彼女がもつ二つの人工精霊がせっせとガラス窓の時間を戻している。その後方には両儀式が立っており、面白くなさそうな表情でドールを見張っていた。
「終わったわよ、これで文句はないでしょう」
水銀燈はまるで悪びれた様子もなく、逆に感謝しろ、とばかりな態度を取っている。
「とにかく、もうここに用はないわ。こんな不気味な所はごめんよ」
橙子の抗議の声を無視し、水銀燈はその場を立ち去ろうとするが真紅が呼び止めた。
「何よ?」
「言ったでしょう。貴女を待っていたって」
「私は待たれる理由がないわね」
「あるわ。貴女もnのフィールドの入り口を探していたのでしょう?」
「だったらなんだって言うのかしら、貴女は知っているとでも?」
「そうよ」
「ふーん……」
と耳障りに水銀燈は呟き、紅玉の瞳を真紅に向けた。
「ならとっとと教えなさいよ」
「時期が来れば教えるわ、それまでは大人しくしていてちょうだい。休戦協定といきましょう?」
「ふん、いやよ。貴女の指図なんか受けないわ」
水銀燈は拒否したが、立ち去ることはやめたらしい。事務所の一角に陣取り、面白くなさそうに周りを見回している。
「なんか式みたいだな……」
橙子の呟きを着物姿の少女はまじめに咎(とが)めた。
「おい、オレをあんなひねくれドールと一緒にするな」
見事に全員スルー
式は不快気に舌打ちし、入り口に近いいつもの場所に陣取って壁に寄りかかった。ほぼ正面のソファーには鮮花や金糸雀たちが相変わらず(多少の漫才を絡めつつ)談話に花を咲かせている。窓側に視線を向ければ自席に戻った橙子が片手にコーヒーカップを持ち、さめた視線でスポーツ新聞を読んでいる。そのまま視線を橙子の右奥に進めていくと机の上で大人しくしている(と思われる)水銀燈と目が合った。
「ふん」
というように、第1ドールはすぐに目を背けてしまった。
(オレとアイツが似ているだって? 冗談じゃないぜ)
なんとなく他者を寄せ付けないまるで同種そのものを嫌っているかのような孤高さが似ているといえば似ているのだが、本人は(いやどっちも)同種などと言われるのが心外だった。
side2 【空の境界・第三章のバトルシーンは五章のバトルシーンを越えてると思う】
「シキ?」
金糸雀はソファーからちょっとだけ顔を出し、壁に寄りかかってたたずむ一重姿の少女を呼んだ。
「なんだ?」
「こっちに来てみんなと話すかしら」
「いいよ、オレは」
金糸雀が悲しそうな顔をした。式は思わずたじろいでしまう。
「シキは独りがいいの?」
緑色の瞳は疑問を呈しているようだった。
「かもしれないな、群れるのは好きじゃないんだ」
「素直じゃないのね。あの子と同じだわ」
その声は真紅だった。優雅なたたずまいのままティーカップを手に持っている。その姿は気品のあふれた貴族の令嬢のようであり、殺伐とした事務所内では違和感があった。調度の高い、それこそアンティーク品で囲まれた部屋こそ、第5ドールの魅力を存分に際立たせるであろう。
「シキ、貴女はようやく多くのしがらみから解放されたのではなくて?」
式は、真紅がなぜいきなりそんなことを言い出したのか驚いたが、その伝達の犯人が舌を出している鮮花だということに気がついた。
「あなたの能力は計り知れないもののようね。その力を巡って戦いに身を投じたことも聞いたわ。あなた自身を形成していたもう一人の『識』のこともね」
余計なことを言いやがって、と式は鮮花をにらんだが、優等生の美少女は全く意に介していない。平然と紅茶をすすっている。
「貴女は『識』というもう一人の人格を失ってからずっとその隙間を埋められずに日々を暮らしていたようだけれど、今はちがうのでしょう?
「 」(カラ)だった隙間は仲間のおかげで埋まりつつあり、「識」から解放され「式」だけで行動できるようになったのよね。人との繋がりを嫌いつつも、貴女を救い成長させたのはその人との交流よ。これからも貴女は自分の衝動と戦いながら生きていくのでしょう。だからこそ人と人とのつながりと出会いは大切にするべきではないかしら?」
式は黙ったままだった。無視はしていない。長い間運命を背負い戦い続けてきた「ローゼンメイデン」というふしぎな存在の言葉は、死を司る魔眼をもつ少女の心に少なからず響いているのかもしれない。
「シキ、貴女はもっと周りの人間と言葉をやりとりすることが必要だわ。一語一語はたあいもないけれど、そこからつむぎだされる言葉はとても貴重で心に残るもの。生きていなくては決して触れられないやりとりよ。貴女は変わっているのだから、これからも変わることができるはずよ。人は成長するのだから」
(人は成長するのだから……)
いい言葉です。いろいろな意味と可能性を秘めた言葉だわ。当たり前のようでその歩みは決してスムーズではないけれど、本人も気がつかないうちに人はいつの間にか先を進んでいるもの……
「今の私がそうね」
藤乃は、儚げに微笑みティーカップのなかに視線を落とした。長い間、自分の存在意義を追い求めてきた少女は心を閉ざし、世間から隔離された状態で日々を過ごしていたことがあった。一歩も前に進めず、後退することが多かったかもしれない。人外の能力をもってしまったがために父親に嫌われ、世間や母親からは引き離され、少女は親に認められたいがため、自分の存在意義を見出したいがために取り返しのつかないことに手を染めてしまったのだった。
そして、一つの狂いが浅上藤乃に破滅をもたらしそうになったとき、両儀式という黒髪の美しい死神と闘ったことで大きな転機を迎えることになったのだった。
それまでは本当に目立たないようにひっそりと生きてきたのに……
今は親友に支えられ、思わぬ人に助けられ、浅上藤乃はようやく時間をかけて前に進もうとしているのだ。
「ねえ式さん、みんなとこちらでお話しましょう。なんでしたらいつかの闘いの話でもしましょうか?」
にっこり笑ってとんでもないことを口にした藤乃に対し、鮮花の片手が素早く親友のふくよかな胸を打つ。
「藤乃、それってちょっと違うからやめようよ。話が楽しくないし……」
「えっ? そうですか、私は楽しかったですよ」
鮮花が返答に窮していると、壁によ寄りかかっていた式が頭をかき、ソファーに向って呟いた。
「やれやれ、人形に説教されるとは思わなかったぜ」
「あら、光栄に思ってほしいわね」
真紅はくすりと笑い、式に座るようソファーを叩いた。それを後押しするかのように金糸雀が手招きする。
「まったく、少しだけだぞ」
式はそう言ってだるそうに、しかし確実にソファーに向って歩を進めた。その途中に角のほうで「いかにもつまらなそうにしている第1ドール」に声を掛ける。
「おい、お前──水銀燈だっけ? お前もこっちに来て話でもしたらどうだ。闘っている姉妹同士で面と向って話すなんて滅多にないチャンスだろ?」
「死んでも断るわ!」
と瞬間的に断固とした拒絶が返ってきた。
「ふう、お前も案外頑固だな」
式はあきれたように呟いてこめかみの辺りを人差し指でかき、何かを決意したように方向を転換して水銀燈の前に歩み寄った。
「ちょ、何をするのよ! 離しなさい、離せ!」
水銀燈の猛烈な抗議と抵抗などものともせず、式は第1ドールをひょいと抱き上げていた。
「団欒ていうのは家族みんなでするもんだろ。お前だけ仲間はずれにするわけにはいかないんだよ」
「大きなお世話よ。私を馴れ合いの真紅たちと一緒にしないでほしいわ」
「じゃあ、社会勉強だ。礼儀作法ってヤツを教えてやるぜ」
お前が言うか! と橙子が苦しそうに笑っていたが式は無視し、ビルの女主人に訊いた。
「おいトウコ、あれあったろ例の首輪」
問われた女性は式が何をやろうとしているのかすぐに理解したようだった。
「束縛の首輪か? なるほど、強制的に第1ドールを席に付けようとはお前も酷いヤツだな」
「うるさい、はやくよこせ」
ほら、と言って橙子は引き出しから取り出した銀色の首輪を式に放り投げる。受け取った黒髪の少女は抵抗するドールをソファーに座らせると、その瞬間に合わせて首輪をドールの細い首に当てる。首輪は青白い光を放ち、ドールの首にぴったりとはまってしまった。
「なんなのよこれは……外しなさい!」
水銀燈は、はめられた首輪を取ろうとするが何をどうやってもとれない。次に怒りの形相のままその場を飛び立とうとした。
「えっ?」
飛べない。立ち去ることもできない。強制的にソファーに戻されてしまう。
「えーと、これってなんなの?」
鮮花が目を複数回まばたかせて不思議アイテムの謎を問うた。
「ああ、それはね」
と応じたのは蒼崎橙子だった。夕日に染まる窓を背景に稀代の人形師は愉快そうに笑った。
「さっきも言ったが、それは束縛の首輪といってな。その名の通り相手を一定時間必要な場所に強制的に留めておくアイテムさ。以前、中東辺りを旅行したときに手に入れたんだが意外と使う機会がなくてな。なんでもその昔、教育だか拷問かに用いられたものらしい」
「はぁ……」
鮮花はあきれている。藤乃や真紅たちもほぼ同じ反応だ。
「あれだ、留めておきたい場所でそいつに霊力をこめて相手にはめるんだ。霊力を込めた分だけ対象者を一定時間そこに縛り付けることが出来る。そうだな、青白く光ったから効力は一時間半くらいだろう」
「なっ! 冗談じゃないわよ。取りなさいよ」
水銀燈は猛抗議し、自ら首輪を外そうとする。
「ああ、霊力がなくならない限り外すことは不可能だ。そうそう無理に外そうとするとリスクが加算されることになっているようだ。今ので30分は増えたな」
橙子が素っ気ない口調で忠告すると、水銀燈の手が止まった。人形師に鋭い視線を向けるが相手は平然としている。
「ここは私のテリトリーだからねー、礼儀作法は守ってもらおうか。みんなと水入らずで楽しんでくれたまえ」
やはり鬼だ、と鮮花は心から思った。礼儀作法などともっともらしいことを理由に挙げたが、きっと単純に「面白いから」に違いない。師の悪い癖だ。残念なことに黒桐幹也は戻ってきそうにないし、もう一人の青年はアルバイトなのにかわいそうに北国に出張させられていた。橙子の嗜好を止められる人間は皆無といっていいだろう。
「なあ水銀燈、君がそこまで真紅を嫌う理由をあえて尋ねはしない。けれど話を聞く限りでは君は戦い意外で集うことはないそうじゃないか。ある意味戦う必要もなく姉妹たちと話をできるというのは日常で言えない本音をぶつけるチャンスじゃないのかね?」
「必要ないわ。虫唾が走るだけよ」
「そんなことはないと思います」
静かだが諭すように呟いたのは浅上藤乃だった。少女の赤みのかかった瞳が水銀燈にむけられた。
「私は父から忌み嫌われています。本当の父ではありません、母の再婚相手です。一族の分家だった父は私の力のことを知っていました。だから私から母を引き離し、もってはいけない力をもってしまったために子供の頃から回りに不気味がられていました」
水銀燈の表情が変わった。真紅たちも中世的な美しさの少女の突然の告白に驚いている。
「私の能力は痛みを感じている間だけ行使すことができます。そして目に映る全てのものを捻じ曲げることが出来るのです」
鮮花が懸念を示すように藤乃の肩に手を乗せて止めようとするが、かつて心に大きな傷を抱えた少女は首を振って拒絶した。
「父は私の能力を封じ込めるため、私に薬を投与して痛みを感じない身体にしてしまいました。そこから私の孤独が始まりました。父は人外の能力をもつ私を隔離したかったのでしょう、格式は高いけれどほとんど監獄のような全寮制の学校に追いやられました。何をしても痛みや感触を感じられず、生きている実感もなく、浮いたような状態で私はそれまでを生きてきました」
浅上藤乃の表情が苦痛を思い出すかのように沈んだ。式は黙って聞いている。水銀燈は誰かにその姿を重ねたように藤乃をまっすぐに見つめていた。
「私は必要のない人間、生きている実感もなく空虚な時間が過ぎていくだけ。誰かに肩を叩かれても、ほっぺをつねられても何も感じない身体でした。そして私は自分の存在意義を確かめるために……」
「だめよ藤乃、もういいわ、もういいのよ」
鮮花は親友を抱きしめ、その先のことは言わないよう訴えた。それでも浅上藤乃は自分と同じように心を閉ざす第1ドールに声を出して言いたかった。
「私は──」
「やめて、うんざりよ!」
片手で制したのは水銀燈だった。紅玉の瞳で藤乃を一瞥し、迷惑そうにそっぽを向いた。
「そんな陰気な告白なんか聞きたくないわ」
その酷い言葉に鮮花はさすがに我慢がならなかったのか、眉間を寄せて水銀燈に手を伸ばそうとした。
それを両儀式が無言で止めた。
「しき?」
魔眼を有する少女は首を横に振り、視線で“オレに任せろ”と言っていた。鮮花は仕方なく手を退ける。
ムスッとした水銀燈に式は話かけた。
「オレもお前と同意見だ。過去の陰気な告白なんか聞きたくない。お前は何の話ならいいんだ?」
式のまさかの発言に鮮花と藤乃は意表を突かれ唖然としている。水銀燈は「脇役」の反応など目もくれず尊大な態度で一重姿の少女を見上げた。
「そうね、そこのお馬鹿さんたちの間抜けな話ならいいけど」
普段なら該当するドールたちは猛抗議するところだが、水銀燈の意外に素直な反応に耳を疑っていた。
つまり、水銀燈は話をすると言っているのである。史上最大の事件であり、真紅や翠星石などは本気で何かかが起こるのではないかと背筋を凍らせたものである。
式がにやりと口元をわずかに緩めてソファーに腰を下ろした。
「ふーん、いいだろう。お前の言うドールたちの話をぜひたっぷり聞こうじゃないか」
翠星石があからさまに嫌な顔をしたが、真紅と金糸雀はとりあえず気まぐれひねくれドールのまさかの『気遣い』を感じ、付き合う気になったらしい。
もちろん嫌々だが……
side3 【劇場版空の境界・第三章の浅上藤乃のヤンデレ度はけっこうなものです】
藤乃が笑顔を取り戻し、ドールたちに告げた。
「では、紅茶を淹れ直してきますね。水銀燈さんもいりますよね?」
「まずいのは許さないわよ」
拒否するとばかり思っていた真紅はまじまじと第1ドールの横顔を見つめた。好敵手のくるくると変わる心情をいまいち理解できないと言いたげである。
「なに? なんか文句でもあるのかしら。わざわざくだらない話に付き合ってあげるのだから、心の奥からありがたく思ってほしいわね」
水銀燈は当然のように言い真紅から視線を逸らせると、なぜか突っ立ったままの人間の少女二人をけしかけた。
「何をぼーっとしているのかしら、とっとと紅茶を淹れて来なさい!」
「「は、はい! すみません」」
藤乃と鮮花は頭を下げ、お互いに微笑んでそそくさと台所へ駆けて行った。
「お前、素直じゃないな」
式は、水銀燈に向ってぼそりと呟く。水銀燈は気分を害されたように腕を組んで怒った顔になった。
「うるさいわね、いちいちくだらないことを言うと談笑とやらをブチ壊してやるわよ」
「わかったわかった、オレも詮索は嫌いだ。好きにやってくれ」
妙に噛み付かれるな、と式は感じつつ黒桐幹也との会話を思い出し、自分も水銀燈と同じではなかったかと少し嫌悪感を覚える。
「いや、オレはここまでひねくれていないぞ」
うんうんと頷く式は、真紅たちに奇妙な視線を向けられていることに気づき、コホンと咳払いして話題を転じた。
「それで水銀燈、どんな話を聞かせてくれるんだ?」
「そうねー、私が真紅の腕をジャンクにしてあげたところから話しましょうか?」
まぶたをヒクヒクさせる真紅に一ミリグラムの遠慮もせず、水銀燈は淡々と話はじめる。
基本的にこのまま水銀燈の真紅に対する武勇伝が続けば本格的で取りとめのない戦闘へ発展しただろうが、鮮花と藤乃が戻ってきてからは話の内容に崩壊を感じ取った鮮花と橙子の巧妙かつ強引なフリで、いつの間にかそれぞれのマスターに関する話に変わっていた。
「へえー、金糸雀ちゃんのマスターはOLさんなのね」
「そうなのかしら鮮花。カナは“みっちゃん”て呼んでるの。みっちゃんはね、とーっても美人で優しくてがんばりやさんなの。カナもみっちゃんが大大大大好きなのかしら」
「うらやましいですね。そばにいてもらいたい人がそばにいるなんて」
「藤乃はいないのかしら?」
「いるような、いないような──今の私には黒桐さんをはじめ皆さんがいるから寂しくなんかないです」
とても満ち足りたように少女は微笑んだ。一連のやり取りを耳にした魔術師が新聞の影から顔を出して声を上げた。
「嬉しいことを言ってくれるね、浅上藤乃」
声のほうに振り向いて、少女は軽く会釈した。
「蒼崎さん、お世辞ではありません。ここに出入りしてから世界が広がりました。なによりも私を受け入れてくれる皆さんの存在を嬉しく思います。私、不器用ですがこれからもよろしくお願いします」
「まあ、そんなにかしこまらなくてもいいよ。これも縁だからね。君の好きなようにするといいさ」
「ありがとうございます」
「なんだか話が逸れていないか?」
式があきれるようにタイミングよく呟くと、鮮花と藤乃はくすくすと、翠星石と橙子は苦しそうにくっくっくと、真紅は声を立てずに笑った。水銀燈はというと話題を変えられて不満げだったが、その口元はわずかに緩んでいた。
ささやかな喧騒が過ぎ去ると鮮花がティーカップを手に取りながら金髪のローゼンメイデンに話を振った。
「じゃあ、真紅ちゃんのマスターについて聞きたいなぁ」
「あまり期待しないでちょうだい」
「ヤツはチビで眼鏡で引きこもり野郎ですぅ」
翠星石が躊躇無く暴露する。首をひねったのは鮮花だった。
「引きこもり?」
「そうね、ちょっと問題があるけれど根は優しくて思いやりのある子よ。ジュンはわたしと翠星石のマスターであるのよ」
これを耳にした橙子は新聞の間から顔をだす。
「ほほう、ローゼンメイデンを二体も所有とはうらやましい限りだな」
「ええ、ジュンは人形師としての才能も持ち合わせているわ」
それを皮切りに真紅と翠星石のマスターである「桜田ジュン」という少年についての話題は盛り上がり(一応、水銀燈もブツブツ文句を言いながらも聞いていた)楽しくも限りある時間はあっという間に過ぎ去っていった。
side4 【ドールたちの中では水銀燈が一番人気なのかな?】
──19時17分──
「こんなもの!」
ようやく怪しい首輪の拘束から解放された水銀燈はそれを引き外し、面白そうに笑っている魔術師に思いっきり投げつけた。
「水銀燈、なかなか貴重で水入らずな時間が過ごせたのではないかね?」
橙子は、たやすく首輪をキャッチして嫌味を口にした。
「おかげさまで貴重な時間を浪費したわ」
負けじと水銀燈が不快な感情を込めて言い返すが、やや歯切れを欠いたのは睨みつけた相手が実はとんでもなく恐ろしい魔術師だったからだろう。
水銀燈は橙子から視線を背け、真紅に振り向いた。
「真紅、お子様タイムは終了よ。いいかげんnのフィールドの入り口を教えなさい」
「そうね約束だもの、時間も時間ね」
青い瞳のドールは優雅にソファーから立ちあがった。彼女に続き翠星石と金糸雀も席を立つ。
「行っちゃうの?」
鮮花だった。いつも凛然とした顔が悲しげだ。その隣で見守る藤乃も実に残念そうにため息をついている。
「ええ、私たちは戻らなければいけないの。それぞれのマスターが待っているし、そこが帰るべき場所であるからよ」
最初に返事をしたのは浅上の令嬢だった。
「そうですね。桜田くんも心配しているでしょうね」
「ふう、そうね。残念だけど帰るべき場所に帰らないとダメよね」
「藤乃、鮮花ありがとう。とても楽しい時間だったわ」
真紅はにっこり笑って右手をそれぞれの少女に差し出した。温かで心落ち着く感触──
二人の少女も努めて笑顔で真紅の手をとった。
「ええ、こちらこそ。ローゼンメイデンに出会えたこと、一生の思い出になります」
「ありがとう、私たちもあなたたちに出会えたこと、とても嬉しいわ」
ドールのマスターやごく限られた人間としか話したことのない真紅たちにとって、日常の中では決して交差することのない繋がりのない人間との交流は新しい発見と驚きの連続だった。その存在ゆえに理解し、受け入れることができない人間の方が圧倒的なのだ。だからこそ人工精霊によって「マスター」は慎重に選ばれる。
しかし、式たちは違った。真紅たちを奇怪な存在として拒絶せず──いや、正確には彼女たちが異質だからこそドールたちをいとも簡単に受け入れたのだろう。日常と非日常の狭間に生きる人間だからこそ、異質の存在にも判断のレンズを歪めることも抵抗もなく順応したのだ。
それは本当に小さな確率。
両儀式が漆黒の瞳にそれぞれのドールを映した。
「お前たちとの時間、悪くなかったぜ。真紅の言うやり方でアリスへの道が開けるといいな」
「ありがとう。あなたはゆっくりでいいから自分を取り戻しなさい。しがらみから解放されたあなたならきっと出来るはずよ」
こそばゆそうに式は頭を掻いた。
「やれやれ、オレそんなに生き急いで見えるのか?」
「あれだな、少し前までは積極的に死地に飛び込んでたろ? 今もたいして変わらんがね」
横槍は橙子だった。タバコをくわえた状態でなにやら資料に目を通しており、独り言なんだよ、と強引に主張している。
式は何か言おうとして視線を下げた。そこには別れを惜しむかのように緑色の瞳で彼女を見上げるロールおさげのドールがいた。
「シキ……」
式は、低くつぶやく金糸雀に目線を同じにしてローゼンメイデンの小さな頭を撫でた。
「短い間だったけど面白かったぜ。交差することのない日常の中で出会えたこと、オレはずっと忘れないと思う。オレもがんばるからお前もしっかりしろよ、頭脳派ドール」
「うん、かしら……」
金糸雀の潤んだ大きな瞳から一滴の涙がこぼれ落ちた。式は白純の人差し指でそっと拭ってあげる。
「おいおい、同じ現実世界に暮らしているんだろ? ならまた会えるさ。泣くなんて二度と会えないみたいでなんかいやだぜ」
式は微笑んだ。親しい人物に対してもめったに見せないほのかな温かさの香る微笑だった。
「また会うかしら」
金糸雀は笑顔で返し、小さな手を差し出した。
「そうだな」
式はドールの手を取り、しっかりと握り締めて再会を約束した。お互いの視線が重なり自然とまた笑顔になった。
「あのう、お別れの最中にすみませんが……」
控えめな声の主は浅上藤乃だった。遠慮がちな表情は何か言いたいらしい。
鮮花が怪訝そうに尋ねた。
「どうしたの、藤乃?」
「ええ、もしよろしければ記念写真を撮りませんか?」
意表を突いた提案にその場の全員が軽く驚くが、すぐに鮮花と金糸雀が賛同した。
「ということですが、真紅ちゃんと翠星石ちゃんはどうでしょう?」
「私はかまわないわよ。翠星石は?」
「金糸雀の件もあるし、人肌脱いでやるですぅ」
残りは水銀燈だが、橙子に「命令」され不承不承の体で承諾した。その時の第1ドールの何とも表現しがたい反応は真紅たちの間で後々の話のネタになった。
両儀式が雑然とした事務所内を見回した。
「で、撮るのはいいけど、カメラはどこなんだ? トウコが持っているのか」
「私は持っていないぞ、というか何処にあるかわからん」
「カメラはあります」
全員がストレートヘアーの美少女に振り向いた。彼女の両手にはいかにも高そうな一眼レフカメラが収まっている。
「なるほど、アイツの私物か」
式は納得して頷いた。
「ええ、フィルムも入っています。以前、使い方を教わったので問題ありません。三脚は蒼崎さんが持っているようですし」
問題が解決したところで橙子が指示を飛ばした。
「よし、じゃあ始めようかね。浅上藤乃はカメラをこの三脚に固定してくれ」
「はい、蒼崎さん」
「鮮花はそっちのソファーにドールたちを座らせてくれ。構図と順番は任せる。重大だぞ」
「はい、橙子さん」
「式、君は正面のソファーを横にずらしてくれ。三脚がやや低いからレンズ内に入ってしまうからな」
一重姿の少女は軽く舌打ちした。
「なんだよ、オレが力仕事かよ」
「つべこべ言わずに行動しろ。金糸雀にがんばると言ったろ?」
痛いところを突かれ、式はゆるやかな動作ながら邪魔なソファーをずらしにかかった。ドールたちは鮮花の指示でソファーに座る。一応、真紅と水銀燈を隣にすることは避ける。
──五分後──
「では、タイマーを10秒に設定しますね。いきまーす」
鮮花がシャッターを押し、機敏な動作でソファーの後ろに立った。となりに藤乃、中央に橙子、その左隣に式の順番だ。ソファー中央に真紅、その左に金糸雀、右隣には翠星石、水銀燈の順番だった。
タイマーが点滅しだした。橙子がみんなに合図した。
「よーし、いい顔で写れよ」
ほどなくしてシャッターが切られる。異能の人間たちと伝説のローゼンメイデンとの最初で最後の集合写真。ほんの短い時間に築かれた心の交流とちょっとした気まぐれによって生じたありえないはずの出会いが、今日という不思議な時間を彩ったのだ。
side5 【橙子のビルは廃墟な感じです】
──19時52分──
式やドールたちはビルの一階にある倉庫の前に立っていた。真紅が言うにはここに「nのフィールド」に繋がる何かがあるというのだった。
式が薄汚れたドアを開けると埃りっぽいにおいとともに暗い空間に光が差し込む。
「ええと、電気電気…」
式が照明のスイッチを探しあてると一気に部屋の全貌が現れた。6畳ほどの空間には何やらいろいろな怪しそうな物体が無造作に置かれている。
「怪しいとは失礼な。全部私の貴重なコレクションだぞ」
橙子は胸を張って主張したが、当然ながら少女三名の視線は冷ややかなものだった。所長の「全部ムダな買い物」のために社員の青年とアルバイトの青年が頭を悩ませているからである。
真紅が、右の角にある布に覆われた大きな物体に歩み寄った。
「これだわ」
バサリと真紅が布を引くと、その下からは見事な木彫りの彫刻が施された大きな鏡が現れる。その鏡面は倉庫に長い間「保管」されていたにもかかわらず全くと言っていいほど傷ついていなかった。
式が表面をなでる真紅に尋ねた。
「これがnのフィールドの入り口なのか?」
「ええ、そうよ。nのフィールドの入り口となるものは鏡や水、テレビの画面などがあるけど、その該当するいずれも生命のかけらというものを持っているのよ」
橙子が得心がいったように頷いた。
「なるほど、いわゆる魔力を持つに至ったモノたちという考えでいいのかな?」
「そうね、橙子風に言うとそういうことね」
鏡面をなでていた真紅の右手が不意に水の吸い込まれるように鏡の中に消えた。その不思議な光景を間近に目撃した人間の女性四人は思わず驚きと好奇の声を上げる。
真紅が右手を鏡から引き戻した。
「うん、nのフィールドの入り口としては申し分のない生命をもっているわ。さすがは橙子ね、よい目利きだわ」
「そうだろう、そうだろう」
と満足気に肯定しているのは当人だけであり、式や鮮花はいかにも疑わしそうな視線を魔術師に突き刺していた。
「どきなさい!」
突然、真紅たちを押しのけて水銀燈が鏡の中に進入する。式たちに目もくれずという勢いに思えたが、左半身だけを残した状態で第1ドールはぼそりと言った。
「じゃあね、人間たち」
プイと顔を背け、水銀燈は鏡の中に消えてしまった。
「すごいわ……」
と思わぬ台詞を口にしたのは真紅だった。その美しい顔にも驚きが形成されている。
「えっ、鏡に入ったのが凄いの? たしかに凄いと思うけど」
鮮花が答えたが、もちろんそんな当たり前なことに真紅は驚いたわけではなかった。
「あの子があなたたち人間に対して蔑むような言葉を使わなかったわ。お父様以外はあの子にとってはどうでもいいみたいなの。だからこそ、あなたたちに対して礼儀をわきまえたのが驚きなのよ」
「ふーん、そうなのか」
式が素っ気なく呟いた。
「ええ、とても珍しいと思うわ。信じられないけれど敬意を表したといってもいいかしらね」
「まあ、別に嬉しくなんかないぜ。逆に気色が悪いな」
式が肩をすくめて言うと、真紅も同意したように頷き、一体と一人は顔を見合わせて吹き出した。どちらも滅多なことでは素直に内をさらすことはしないのだが、短い時間の中で行われた生彩なやり取りは、そんな両者の心の扉を容易に開け放ったようだった。
三体のローゼンメイデンが鏡の前に揃い、丁寧にお辞儀をして一体、また一体とnのフィールドへと消えていく。最後に残ったのはロールおさげのローゼンメイデンだった。その両手には橙子からもらった魔力の宝石を生成するという小箱が納まっている。
式は、腰を落として金糸雀の緑色の瞳を覗き込んだ。
「いいのか、この箱を開けなくて」
「うん、いいかしら。この箱は式たちとカナたちの思い出が詰まったものかしら。もし開けるとしたら、次に式たちと会うときかしら」
「素敵ですね」
と両手を胸の辺りで組んで浅上藤乃が感動したように呟いた。その隣では黒桐鮮花が瞳を潤ませつつドールを見送っている。
式は金糸雀の頭をそっと撫でた。
「そうだな、次に会う時にみんなでその箱を開けよう。それまで預かっておいてくれよ」
「うん、かしら」
「ああ、そうだな」
現実には二度と会えないかもしれないのだ。彼女たちローゼンメイデンは「究極の少女」を目指して姉妹同士で闘う運命にある。今日の穏かな一日が再び訪れるという保障はない。もし奇跡的に訪れたとしても、その中に金糸雀が含まれているとは限らないのだ。
それでも両儀式は信じてみたかった。
それでも金糸雀は夢に描いていた。
「再会」という約束を……
「シキ、トウコ、鮮花、藤乃、ほんとのほんとにありがとう。戻ったらみんなのことをみっちゃんやジュンやのりにいっぱい、いっぱい話すかしら」
金糸雀はうっすら涙を浮かべて手を振った。その意味は別れではない。だから涙も悲しいわけではない。遊び相手の友達の家から自分の家に戻るだけ。
金糸雀は、心地よい記憶とともにやさしいマスターの元へ戻るのだ。
「また、遊びに来るかしら」
金糸雀は鏡の中に吸い込まれる最後まで手を振り続けていた。
式も鮮花も橙子も藤乃も過ぎ去りゆく時間にしばしの別れを告げて、しばらく手を振り続けていた。
その時間の扉は閉じられた。
side6 【nのフィールドの概念はむずい】
真紅は、涙を拭う第2ドールを気遣うように声をかけた。
「大丈夫かしら、この涙は悲しい涙じゃないかしら。シキたちに会えて嬉しい涙かしら」
「ならいいわ。さあ行きましょう、みんな待っているわ」
ドールたちのいる空間は暗く、無数のドアが浮いている。それがnのフィールド。現実と表裏一体をなす、精神と虚の世界が無数に存在する異空間。繋がる世界は真紅たちでも数え切れないほどだった。
水銀燈の姿は見えない、すでに戻っているのだろう。藤乃の告白を止めた事に対して一言くらい言葉を掛けたかったのに……
ドールたちは異空間の中を飛ぶように進みだした。
ふと、真紅は閉じられた扉に向って振り返った。
「そういうことなのね」
真紅の違和感が解消されたのだ。あの時間はたしかに現実世界だった。ほとんど虚と精神世界で構成されたnのフィールドの中で直接現実世界に繋がる扉は多くはない。誰かの精神世界に繋がっている場合の方が多いのだ。でも、ローゼンメイデンが存在した世界に間違いはない。
ただ、そこは25,000時間ほど遡った世界だったのだ。
nのフィールドに存在した現実世界の過去……
ならば、また出会うこともあるのかもしれなかった。
「不思議なこともあるのね」
真紅はつぶやき、不意に肩を叩かれた。
「真紅、みえたですぅ」
翠星石が指し示した方向には、ドールたちの暮らす未来の現実世界の扉がなつかしげに存在していた。あの扉をくぐれば、また忙しくも温かい日常が始まるのだろう。目を覚まし、鞄を開ければ真紅のマスターがベッドでまだ寝ているのだ。彼女はあきれるようにため息をついて14歳の少年に言うだろう。
「ジュン、いい加減起きなさい。でなければせめて返事をしなさい。あなたは私の下僕? それともマスターなのかしら?」
何も言わないかもしれない。ブツブツと文句を言うかもしれない。仕方なく起き出して真紅のために紅茶を淹れてくれるかもしれない。
いや、きっとその全てだろう。
真紅は、少年の顔をすぐに見たいと思った。
「さあ急ぎましょう。今からなら夕食に間に合うでしょう」
ローゼンメイデンの時間は再び動き出す。
『アリス』を求めて……
──終わり──
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
あとがき
これで短編終わりです。後半、ダッシュした感じでスミマセン。終わらせ方に苦慮しました(汗) 水銀燈が登場した段階でさっさと終わらせるつもりが…
nのフィールドの概念がよくわからんです。原作ではあいまいなようなw アニメ版でも表現はあいまいでしたよね?
いろいろな世界が混在しているのだから、私の考えもアリでしょう?
空の境界・劇場版第七章はどうも四月に入ってからのようです。黄金週間前に封切りかなぁ……
それではご一読いただきましてありがとうございました。
2009年3月8日 ──涼──
修正履歴
誤字脱字を修正。ふじのんの挿絵を削除しました。
2010年3月──涼──
最終修正です。誤字脱字を修正。見直し一部あり。
2011年9月19日──涼──
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇