私たちは悠久の闇を進んでいる
ずっとずっと続く至高の世界
朝も昼もない深遠の世界が
時間という概念を忘れさせてしまう
でも、私たちは刻の奇跡に出会ってしまう
懐かしき人と出会ってしまったのだ
なぜ、よりによってこの人!
まあまあ、もちろんその人に罪はない
だって、顔は同じでも全く違う人
みんな輪廻転生って噂をしているみたい
けれど、つい笑ってしまうのも確か
そんな最中、プロさんに呼びだされた
メンバーを見て絶句した
えーと、えーと
本気なの? プロスさん
返ってくる微笑……
ちょっ、これって同盟の人たちには
絶対に見られたくないかも
──ホシノ・ルリ──
闇が深くなる夜明けの前に
機動戦艦ナデシコ×銀河英雄伝説
第二章(後編)
「生まれ『変わる』時間/なつかしき人に出会う私たち」
Ⅰ
──宇宙暦795年帝国暦486年、標準暦10月3日──
ナデシコ艦内時計時間12時50分
ユリカとラピスが数千億の星々も注目する「睨み合い」をしている頃、ナデシコではある人物に対する話題でもちきりになっていた。
「未来だって納得したね。あの人に会うなんてね」
「生まれ変わりってやつは本当にあるんだね。いや、驚いたよ」
「これって幸なのか不幸なのか微妙だぜ。たぶん後者だと思うけど」
「ま、過去のあのヒトには申し訳ないけど、今のほうが好感がもてることは間違いないよ」
「なんか、かっこいいよね。戦う男って感じじゃん」
ちょうどお昼を迎えていたナデシコの食堂では、まことしやかに「その人物」に対する感想やら批評やら思い出話が飛び交っていた。そのほとんどが故人に対する悪口や笑いのネタの類だが、久々に食堂の空間は明るい雰囲気で満たされていた。
「ホウメイさん……」
ホウメイを手伝う五人の女性クルーもそれぞれ懐かしげな視線を懐の広い女性料理長に向けている。
「そうだねぇ、こんなこともあるんだね。わたしたちはきっとあの人の第二の人生をこの目で見ているんだよ」
ホウメイは目を閉じ、良くも悪くも記憶に残るその人物の姿を思い浮かべて静かにつぶやいたのだった。
──艦内時計時間12時58分──
艦長代行を務める副長のアオイ・ジュンは指揮卓の前に立ち、基地までの案内役を務める「駆逐艦アキヅキ」からの最初の定時連絡を待っていた。その表情はほとんどの乗員と同じく懐かしさとにくにくさが均等に配分されており、身近にその人物と関わっていただけに彼も少なからず感慨深げだった。
──艦内時計時間13時00分──
ピッタリにアキヅキから定時連絡が入ってきた。背筋を伸ばして敬礼する「少佐」にナデシコの副長も倣いつつ、あらためて通信スクリーンに映る人物が故人と瓜二つであることに驚きを禁じえないでいた。鳥気味のあごに突き出た頬、大きめのわし鼻に大きい耳、トレードマークのおかっぱ頭……
ウランフから紹介されたとき、艦橋内は一気に驚きのパロメーターを突破してしまい、彼がエクスバリスの爆発の弾みでボソンジャンプしたのではないかという錯覚にとらわれてしまったほどである。
その顔は、忘れえぬ記憶となって脳裏の引き出しにしまわれていた。
「ムネタケです。本日、最初の定時連絡をお伝えします」
「お疲れ様です。副長のアオイ・ジュンと申します。艦長が所用で席を外しているため私が代行を務めております」
そう挨拶をするジュンには若干の違和感がある。
「そうでしたか、それでは副長殿にお伝えします」
と前置きして、ムネタケ・アキサダ少佐はきびきびとした口調で現時点の位置と今後の予定航路、到着予定時刻をジュンに伝えた。
「以上です。現在のところスケジュールは順調に消化しています」
「それはありがたいですね」
「では次回は15時に御連絡します。ナデシコに異常はございませんか?」
「はい、今のところ問題ありません。ありがとうございました」
「そうですか、ミスマル艦長にもよろしくお伝えください。では」
お互いに敬礼して通信を終了する。
「つくづく似ているな」
とジュンは思う。生まれ変わりというなら当然似ていてしかるべきなのだが、「未来のムネタケ」は彼らの知っている「ムネタケ提督」とはやはり違っていた。まずオカマ口調でなく、年齢も30代前半と若く、目元と口元が引き締まり、軍人としてまとまりがあり、なおかつ職務に真面目だった。
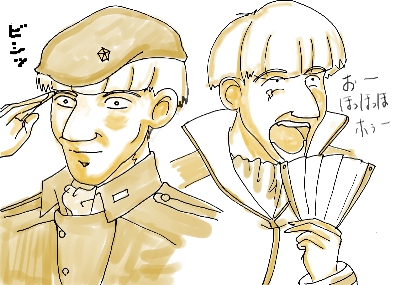
「ぜんぶ同じだったら生まれ変わった意味がないだろ」
と毒舌を吐くクルーもいたが、ナデシコのクルーの大半は輪廻転生を信じる民族で構成されているため、自然と「ムネタケ・サダアキ」の第二の人生について語らずにはいられない。
「どうやら少佐には同盟の首都星に妻子がいるらしいぞ。子供が親に似ていたらかわいそうだ」
「30代前半で少佐とは、そこそこ出世しているな。ま、提督には悪いけど今のムネタケ少佐のほうが実力で出世したって感じがするね」
「あのまともな声と態度には参ったね。あのムネタケ提督がこうも変貌を遂げるとは、さすがは神様だね。顔は元のままだけど」
……懐かしんでない。話のネタじゃん。
「けっこうひどい言われようね。少佐に罪はないと思うけど」
と火星丼を食べながらエリナがムネタケ少佐を擁護する。
それもそのはずで帝国軍の巡航艦3隻に追われていたナデシコを発見し、近くでアキヅキの捜索をしていた第10艦隊に通報したのは、ほかならぬムネタケ少佐だったのである。本隊から離れ第208哨戒任部部隊を形成していたアキヅキは、機関故障で周辺宙域を漂流中に追われるナデシコを監視衛星からの映像配信で捉えたのだった。彼が機転を利かせた結果、ナデシコと乗員221名は九死に一生を得たのである。だからムネタケ少佐に感謝することはあっても笑い話のネタにする筋合いなどないのだった。
◆◆◆
「やあ、エリナ君。となり空いているかい?」
「空いていません」
と即答され、彼女以外座っていない席を見てロン毛で背の高い青年は苦笑いした。
「つれないねぇ、昨晩、何か悪いことでもしたかい?」
カッとエリナの目が開き、思わずアカツキはたじろいでしまう。
「アカツキ会長、ご自身の胸によーく訊いてみることです!」
ガタン! とエリナは派手に椅子から離れ、とまどうアカツキを一瞥もせずにどんぶりを返却口に置くと、異様なオーラをまとったまま食堂を足早に出て行ってしまった。
食堂に集う視線が全て若いネルガルの会長に注がれる。
「いや、ちょっと待って、僕は何も悪くないよ。なんで怒っているのか不思議なくらいなんだ」
冷ややかな視線を浴びつつ椅子に腰を下ろし、その理由を考えてみたが、どうにも思い当たらないでいた。
「やれやれ、あのままじゃ協力を仰げないよなぁ」
独語した直後、アカツキはその声で顔を上げた。
「アカツキさん、焼肉定食宙盛りお待たせしました」
テラサキ・サユリだった。艦内食堂で料理長のホウメイを手伝う通称「ホウメイガールズ」と呼ばれる五人の女性クルーの一人であり、170を越えるモデル並みの身長と均整のとれたスマートボディ、長い黒髪をポニーテールにしたなかなかの健康美人だった。凛とした表情と美しい脚線美は艦内でも人気が高く、また実質的にホウメイガールズのリーダーと目されていた。
「やあ、ありがとうサユリくん」
アカツキは、気持ちを切り替えて新メニューをさっそくいただく。彼はどちらかというと洋食派だったのだが、過去形で語られるようにナデシコに乗艦してからはホウメイの作る料理に魅了され、和食系も好きになっていた。
しかし、ナデシコに乗艦してからはや数ヶ月、木星蜥蜴との激しい戦闘の後でも平気で大盛りを食べていたが、ここにきてメニューを一巡してしまい、さてどうしようかと悩んでいるところにホウメイが「焼肉定食の宙盛り」を新メニューとして加えてきたので注文したのである。
ちなみに「宙盛り」とは──宇宙のような盛り方らしい。
少しためらった後、サユリはアカツキにたずねた。
「アカツキさん、エリナさん、ずいぶんご立腹のようでしたが何かあったんでしょうか?」
ロン毛の青年は箸を止めて複雑な顔をした。
「うーん、原因を探しているんだけど、どうも思い至らないんだよね」
エリナが聞いたら宇宙に放り出されるだけではすまない真剣な大ボケだった。
「アカツキさん、差し出がましいようですが、何か思い当たることがあればすぐに謝罪したほうがいいですよ」
「ありがとう、サユリくん。ご忠告、ありがたく受け取っておくよ」
この際だ、サユリくんの言うように、とりあえず謝っておいたほうが無難かな? といって、トンチンカンなことになったら本末転倒だしね。
自嘲気味に笑った青年は、今、彼に必要で有益な依頼を長身の美人にした。
「すまない、サユリくん。お茶をもらえないかな」
「はい、緑茶、煎茶、玄米茶とありますが、どれになさいますか?」
「そうだね、もちろん」
トレイを胸に抱きしめて待つポニーテールの美女に、ロン毛の好青年は当たり前のように言った。
「もちろん、玄米茶で」
◆◆◆
昼食を終えたアカツキは、なんとなく落ち着かないので愛機整備のため格納庫へと歩を進めていた。途中、幾人かのクルーとすれ違い挨拶を交わしたが、遠ざかる彼らから漏れる話題はあの駆逐艦の艦長に集中していた。
「ムネタケ提督がもしあの世とやらで聞いていたらさぞ喜んだだろうな。自分は忘れられていないって」
出世欲に駆られ、指揮官としても上司としても失格だったムネタケ・サダアキ提督。ナデシコ乗員で彼を尊敬していた者など皆無であったことは事実である。
そのムネタケが機密漏洩の責任を軍上層部から問われ、彼は自暴自棄になり、ウリバタケが密かに試作したエクスバリス(欠陥機)に乗って暴走し、自爆するようにこの世を去ってしまった。
「わたしだって、正義を信じていたわよ……」
暴走する直前、閉店間際の食堂で一人たたずんでいた彼はそんなことをつぶやいていた、とホウメイから事件後に聞くことになった。
「でも、ムネタケ少佐は自分の正義を貫いているようだね」
アカツキは、それこそ感慨をこめて独語した。スクリーンに映ったムネタケ・アキサダ少佐の目は生まれ変わりと呼ぶのにふさわしい活力と生気に溢れており、己の果たすべき役割と責務をなんら疑うことなく遂行しているように感じられたのだ。姿かたちは同じかもしれない。だがその個人は──器は違っていた。一方は退廃と失望、一方は健全と希望を体現していた。
「なるほど、確かに彼は生まれ変わりだよ」
そして、今ははるか未来だよ。おもしろい。
「面白すぎる」
アカツキはかすかに笑った。この状況が「偶然」というのならその原因と過程とはなんだろうか。それが「必然」だというならば、何を望まれて僕らは遠い未来? へジャンプしなければならなかったのだろうか?
この二つの状況は違う。だが、問う内容は同じだった。
「僕らがなすべきことは何か」
アカツキは考える。その時間が3日だろうと1ヶ月だろうと1年になろうと起こってしまった状況を楽しまないわけにはいかない。いや、利用しないわけにいかない。万物の出来事にはすべてに意味があるのだという。還るにしても留まるにしても、やることはやっておかないといけなかった。
それが、アカツキ・ナガレの存在する意義でもあるのだから……
青年は、格納庫に通じるドアの前に立った。
「さて、最初の扉を開けるのは誰かな?」
Ⅱ
ウリバタケ・セイヤは昼食もとらずに格納庫に残り、整備ドックにあるエステバリスを一機一機、神妙な顔つきで見上げていた。その深く思考に満ちた表情は普段の陽気さからは逸脱しており、真剣さというよりはどこか思いつめているようでもあった。
「やあ、班長、どうかしましたか?」
その響きのよい声はアカツキ・ナガレだった。長身でロン毛の青年は歩調に無駄もなくウリバタケに歩み寄った。
「おう、アカツキ会長か。メシ喰ってたんじゃないのか?」
「終わりましたよ。いま艦内全員、ムネタケ少佐の話題で持ちきりでしてね。僕は驚くのは一度でたくさんなので、こっちでエステの調整でもしようかと思いましてね」
「ほお、仕事熱心だね。戦闘があるわけでもないのによ」
若干の皮肉が込められていたようだが、アカツキは意に介しない。
「そうですね。一応、僕もエステのいちパイロットですから、不測の事態に対応できるよう愛機の状態をチェックするのは当然です」
「さすがはネルガルの会長さんだぜ、万事に慎重だね」
「よしてください、僕もヒマを持て余しているだけですよ。それに今のアカツキ・ナガレに会長という敬称はふさわしくない。この時代にはネルガル重工は存在しないのですからね。いや、そもそも存在していたとしても、大昔の会長に用事なんかありませんよ」
ちげえねえ、と言ってウリバタケは笑ったが、アカツキの次の言葉に笑いを収めてしまった。
「ウリバタケさんこそ、浮かない顔でエステなんか眺めてどうしたんですか?」
「なーんだ、見られちまってたのか。いや、なに……」
ウリバタケは一度視線を外し、再び目の前のエステバリスを仰ぎ見た。ネルガル重工の粋を集めた全高6メートルあまりの人型機動兵器である。彼はこの美しくも強力な可能性を秘めた機体を見た瞬間にその魅力に取り憑かれてしまい、以後、木星蜥蜴と激しい戦闘の中で、まるで子供でも愛しむかのようにエステバリスの整備と性能アップに心血を注いできたのである。だからこそ、その汎用性と機動力、攻撃力は数多くの木連兵器を葬ってきたことで証明されているはずだった。
「俺たちは戦えるのかなってな」
ウリバタケはエステバリスを見上げたままだった。アカツキも愛機を見上げ、整備班長に言った。
「戦えると思いますよ。僕らが戦おうと思えば戦えるんじゃないかな」
「ずいぶんおき楽なセリフだねぇ。俺たちは下手をすると1400年後のテクノロジーとまともにぶつかるかもしれないんだぜ。
いつ元の時代に戻れるかわからない以上、何もせずとんでもないスケールで戦争している二つの勢力のうちの一つとかかわっちまったからには、ただ待つことなんかできるはずがないだろう?」
ウリバタケはアカツキに視線を移した。ロン毛の青年は愛機を見上げたままだった。
「そうですね。ですが、まだほんの一部を知っただけの今、悩んでも始まらないと思います。僕らは助けてくれた同盟のことも敵対する帝国のこともよく知らないんですからね。戦えないと悩むにはまだ早すぎますよ」
「なるほど。敵を知り己を知れば百戦危うからずということか。双方を知ってもいないのに心配してどうするかってことかな」
「まあ、いきなり帝国軍の巡航艦に撃沈されかかったといって戦えないというわけじゃないということです。要はどう戦うかです。僕の推測の範囲になりますが、同盟の軍艦一つをナデシコと比べた場合、技術そのものにたいして差があるとは思えません。もちろん同盟にあってナデシコにないもの、またその逆もあることでしょう。
もともとナデシコもエステバリスも古代火星人が遺したオーバーテクノロジーから生まれたものですからね。彼らが長い年月をかけて培った技術は未来と比べても遜色ないと感じます」
「なるほどねぇ……」
ウリバタケは、四角い眼鏡をキラリと光らせてうなずいたが、アカツキが意図的に触れないでいた現実に気がついていた。彼は根っからの技術畑の人間として、機械いじりと油と技術開発に情熱を注いできた。いわばそれなりに一般人として生きてきたのだ。
そんなプロの軍人でもないウリバタケでも、間近で木星蜥蜴との戦争を見てきたからこそ、直感的にわかってしまうことがあった。
いや、そう決めてかかってしまうのはいささか性急すぎるかもしれない。「ナデシコ単艦」でも戦える任務はあるだろう。ただし、かなり条件が限られてくることは疑いがない。
それは戦争規模があまりにも違うからに他ならない。人類はウリバタケが生きた時代よりはるか一万光年以上に生活圏を拡げており、銀河規模で戦争をしているのだった。その規模たるは同盟軍の通常編成の正規軍一個艦隊だけで12,800隻におよび、決して数だけではない強大な艦隊が12個艦隊も存在するのである。しかも、各星系におかれた辺境星系の守備艦隊だけで軽く地球連合宇宙軍の一個艦隊に匹敵してしまう数だという。
そしてあろうことか、同盟と敵対する帝国軍の軍事力は同盟を凌駕するというのだ。加えて「距離」という無限の敵が立ちはだかっている。
ウリバタケは、それらのことを知ってから、ナデシコの気質というものを充分熟知しているからこそ言えることがあった。もし、ナデシコが戦うことを決断したとき、後方のほうでのこのこと安全な場所にじっとしているはずがない。絶対に前線に飛び出して自ら道を切り開こうとするだろう。
そうなったとき、数は力である。戦力差をどう埋めるかが問題となるはずなのだ。
「もしかしたら、そのときはウランフ提督の艦隊に所属するのか?」
いや、それこそ性急すぎる考えだ。そこまでこの時代にいるとは限らない。ユニットが早く修復される可能性もあるのだ。突然、今にでもジャンプが可能になるかもしれないのだ。
しかし、残念ながら未来の状況を楽観視していないのも確かだった。
「最悪の状況を考えろ。成功しているうちは流れに乗っかればいい。だが、失敗したときは対処法まで考えるのがプロってもんだぜ」
ふと、ウリバタケは父親の言葉を思い出した。物事には必ず「始まりと終り」があるように、行動そのものには「成功」と「挫折」がつきまとう。人は常に成功することだけを考え、失敗したときのことを考えるのは消極的だとさえ言う。
それは違う、と父親は言ったのだ。成功ばかり考える人間は現実から目をそむける傾向にあり、失敗ばかり考える人間は現実そのものに最初から悲観している。 最良のシナリオと最悪のシナリオ。その両方を考えるのがプロなのだ。コケたときのことを考えるのは対策を容易にする。完全でなくとも、突発的に対応するよりはるかに傷口は小さくて済むのだ。
「いいときは何をしてもいいことが続くものだが、悪いときは何をしても悪いじゃ済まされない。傷口を最小範囲でとどめること、自信の喪失を最小限で防ぐことも大切なんだぜ、セイヤ」
ウリバタケは当時、父親の言うことがよくわからなかったが、木星蜥蜴と戦ううちにその重要性を認識したのだった。
しかし、戦闘が専門でない整備班班長が熟考すべき点は別にある。それこそ彼が重点を置くべき最悪のシナリオに対応した対策だった。
「そうだな、やっぱりあれだよな」
ウリバタケの思考を察したかのように隣から声がした。
「ウリバタケさん、もしエステが通じなくても、そのときは班長がちょいちょいと強化してくれれば問題ありませんよ」
ウリバタケは、ようやく破顔してロン毛のパイロットに振り向いた。
「ちげぇねえや。こんなこともあろうかと、っていうのが俺の性分だしな」
今度は豪快に笑った。やれやれ、ネルガルの会長とはいえ若造に励まされるとは、まだまだ俺も青いな。そうだな、人それぞれに役割というものがある。慣れない戦術だの戦略だのに首を突っ込んでもどうにも思考が至らないことは目に見えている。戦う方法は艦長やアカツキたちに任せておけばいい。俺のできることはナデシコとエステバリスを常に最高の状態に保ち──時には強化することが仕事なのだ。
「やることをやってやるぜ。最悪のシナリオってやつを考えてな」
ウリバタケの表情は晴れやかだった。と同時に悩みが消し飛んだ瞬間、彼は急激な空腹感に見舞われ、くるりとアカツキに背を向けた。
「あれ、どちらに?」
「おう、メシ喰ってくるぜ。腹が減っては戦はできんというからな。しばらくあんたにここを任せるぜ」
「ええ、ごゆっくり。新メニューがお勧めですよ」
扉に向かうウリバタケは軽く左手を上げてアカツキに答える。ロン毛の青年は技術に生きる男の後ろ姿を見送ると、愛機に向かって歩き出した。
二人の男が導き出そうとした「ナデシコの戦い方」
アカツキの言葉通り、機体の性能と武装だけが問題ではなかった。洗練された「用兵」という戦争技術がナデシコとエステバリスの前に立ちはだかっていく。
Ⅲ
15時の定時連絡が終了してから1時間後、プロスペクターに呼び出されたホシノ・ルリはミーティングルームに向かって艦内通路を歩いていた。用件についてはプロスペクターは何も言わなかったが、「全乗員に関わる重要なこと」ということで、ナデシコを自動操舵に切り替えて半ば仕方なく、半ば興味をそそられつつ向かっていた。
しかし……
ルリは、ミーティングルームに足を踏み入れた瞬間、後悔した。そこに集まる面子を見て嫌な予感がしたのだ。
「ではルリちゃんも来たことですし、さっそく始めましょう。どうぞルリちゃん、好きな席に座ってください」
プロスペクターが営業スマイルでルリに席を勧めた。少女はそ知らぬ顔で後ずさりしようとしたが、イネスに背中を押される形で席についてしまった。
長方形の机を囲む面子はルリのほかに四人いた。プロスペクター、イネス・フレサンジュ、ミスマル・ユリカ、ゴート・ホーリーである。
ちょっ……これってもしかしてもしかするかも!
ルリは、チラリと隣に座る艦長の横顔を見たが、どうやらまだ悟っていないらしく頭上に少なくとも? マークが三つは浮かんでいる。
愛用の黄色い縁取り眼鏡をキラリと光らせ、プロスペクターが小さく咳き込んでミーティング用スクリーンの前に立った。
「では皆さん。本日皆さんにお集まりいただきましたのは、ウランフ中将よりいただいた同盟に関する資料についてです」
プロスペクターが指をパチンと鳴らすと、スクリーンに都市らしい映像が現れた。
「えー、今映しているのは同盟の首都星ハイネセンの中心であるハイネセンポリスです。そしてここに映っている巨大な立像が同盟建国の父と呼ばれるアーレ・ハイネセン氏です」
直後に映像が切り替わった。そこに映ったのは項目のようであり、大きく分けて6つに分けられていた。
「さて、ウランフ提督がおっしゃっていましたが、我々は長くも短くもこちらに滞在する間、今の時代の方たちと上手く調和を図るために知っておかねばならない基本的な事があります。最初に見ていただいたのはそのほんの一部です。
項目は全部で6項目あります。同盟の歴史、政治、経済、文化、軍事、一般常識です。これらは各項目ごとにわかりやすくまとめられていましたが、それでも一人一人が学ぶには容量が多く、到着予定を明日の17時に控えている関係で全乗員に閲覧させるにも個人差と要領を得ないと判断しました。まあ効率も悪いでしょう。そこで──」
再びプロスペクターの指が鳴る。すると、いつの間にか立ち上がっていた金髪の科学者が冊子のようなものをみんなに配った。そのタイトルを見た瞬間、ルリは直感をのろい、ユリカは驚きの声を上げていた。
「新なぜなにナデシコ・同盟編」
ユリカが確認した。
「えーと、プロスペクターさん、またこれをやるんですか?」
問われたほうの顔は106パーセントほど真剣だった。
「これ、とは心外ですね。フレサンジュ女史と協議した結果、以前と同じく艦内放送を活用するのが最良と判断したまでです。御心配なさらずともすでに放送用のデーターは編集済みですから、あとは台本に沿って以前と同じく進めていただければけっこうです。もちろん、第1回目の放送までに時間はありますから、それまではイネス監督の指示に従ってリハーサルも行います」
論点がずれているような……
ルリがわずかに眉をそびやかして迷惑そうに手を挙げた。
「しつもーん。わざわざ『なぜなに』しなくてもプロさんがデーターをもっと簡潔にわかりやすく編集して放送したほうが効率がよいのではないでしょうか?」
まったくその通りだと思うが……
「それではだめです。おも──皆さんが熱心に見てくれません。以前のなぜなにナデシコは大変な反響をいただき、皆さんは食い入るように放送を見ていただきました。おかげさまでナデシコに対する理解が深まり、今こうして無事にいることができています。
いずれにせよ、短い時間でかつ集中的に学習していただくには、なぜなにが一番です。艦長はナデシコを統べる方として、ルリちゃんはそのナデシコのシステムを操るエキスパートとして、しっかりと責務を果たしていただきますよ」
プロスペクターは一気に言い切った。ちょび髭をなでる彼は満足げに見えたが、発言の直後に本音を吐露しそうになっていたことに気がついていたルリの心境はややあきれていた。
とは言え、プロスペクターの言うことも一理ある。221名の乗員に滞りなく最低限の情報を均一に提供するには艦内放送が一番なのだ。前回のなぜなにの反応はルリ自身が身を持って体験していた。方法に問題があるとはいえ最良と認めざる得ない。
ユリカが立ち上がった。
「わかりました。全責任を負う艦長として新たな『なぜなにナデシコ』に協力いたます。異論はありません」
プロスペクターは部下を説き伏せたような顔でうなずいた。
「さすがは艦長、われらのアイドル艦長ですな。ルリちゃんもよろしいですかな?」
ルリはだまってうなずいた。どう考えても断れる状況ではない。
「ま、いいか……」
どうせ特にやることもないし。
◆◆◆◆
プロスペクターが手にしていた冊子を張りきって開いた。
「それでは皆さん、まず目次からいきましょう。なぜなにナデシコ復活の一ページ目です」
そのとき、ユリカがすまなそうに手を挙げた。
「なんでしょうか艦長?」
「ええと、あのう、なぜなにをするのはいいんですが、そうなると私は以前のように──そのウサギちゃんになるんでしょうか?」
前回の「なぜなに」ではウサギの着ぐるみを身につけて奮闘したユリカだった。その本音としてはいくら乗員のためとはいえ恥ずかしいものであり、できれば回避したいと考えていた。それは解説のお姉さん役として、そんな感じのコスプレをさせられたルリも同じだった。
プロスペクターが穏やかに言った。
「今回は趣向を変えてみようかと考えていますので、以前のようにはなりません」
微妙な発言にルリは一層嫌な予感がした。
「よろしいですかな? では続きといきましょう」
──西暦2198年10月3日、16時18分──
いや、宇宙暦795年標準暦10月3日、艦内時計時間16時18分
はるかな時間を超越し、永遠の夜の中を進むナデシコにて、数ヶ月ぶり? に伝説の艦内放送「なぜなにナデシコ」が新たな信念? の下に復活する。まさに名プロデューサー、プロスペクター率いる精鋭たちの乗員を思う意思の統一であり、(単なる暇つぶしのようでもあり)後に起こるお祭り騒ぎを予感させる出来事であった。
Ⅳ
──翌日、10月4日、艦内時計時間15時22分──
熱狂的な興奮と支持を集めた第一回「新なぜなにナデシコ・同盟編」の放送から約3時間後、同盟軍前線監視基地へと順調に航行を続けているはずのナデシコはどういうわけか停止していた。
「こいつは少し時間がかかるかな」
エンジンルームに駆けつけたウリバタケは頭をかいてつぶやいた。第2相転移エンジンの制御パネルは全体が赤く点滅しており、異常が感知された箇所が同様に赤くぬりつぶされている。
「やれやれ、基地まであと少しだっていうのに、ずいぶん気まぐれなこったぜ。いや、よく持ちこたえたというべきかもな」
ウリバタケは半分、第2エンジンをねぎらう。損傷を受けて停止した第1エンジンより軽いとはいえ、同様に被害を受けた第2エンジンは出力が落ちるものの何とか稼動していたが、ここにきてついにピークに達したようだった。
「2時間だ、2時間。艦長、2時間だけ時間をくれ。うまく真空エネルギーが転移できない原因を探ってどうにもならなければムネタケ少佐にナデシコの牽引を頼んでくれ」
とユリカに報告したウリバタケは、機関員と整備班を総動員してすぐに原因究明に乗り出した。
「ということですので、しばらくナデシコはお休みです」
ムネタケ少佐に報告の後、ユリカが艦内放送で伝えると、ナデシコ全体がささやかな休憩ムードに包まれる。機械的なこととなると出番のないエステバリスのパイロットたちは早々に艦橋を出て行こうとする。その中にはようやく姿を見せたテンカワ・アキトがいた。
ユリカが声をかけた。
「アキト、ラピスちゃんのところへ戻るの?」
元幼なじみの青年はにっこり笑ってナデシコ艦長に振り向いた。
「うん、せっかくだから少しラピスを外に連れ出そうと思う。ずっと部屋に閉じこもっているのは彼女のためにならないしね。みんなと交流すればきっと明るくなると思うんだ」
「そうだね。ずっと独りぼっちだったから不安や怖いこともいっぱいあると思う。アキト、ラピスちゃんを元気づけてあげてね」
ユリカは心からそう言った。ほんの数時間前まで少女とにらみ合いをしていたのだが、先に身を引いたのはもちろんユリカだった。まったく、自分は少女を相手に何を大人気ないことをしているのだろう。たった一人で一年余りも孤独に眠り続けていた8歳の少女の気持ちを考えると、自分を救い出してくれたアキトを慕うのは当然だと考えたのだ。
だから、今のユリカには「アキトをとられる」などという邪推な懸念や嫉妬は全くなかった。
「俺、ラピスの親代わりを引き受けるよ」
という婚約者の決意にも素直に笑顔で応じたユリカだった。
「じゃあユリカ、ちょっと行ってくるね。たぶん、ラピスを艦橋に連れて来るかも」
「うん、みんなで歓迎するね。ラピスちゃんが喜んでくれるように」
アキトが温かい笑顔で応じ、手を振って艦橋から出て行く。その眼差しにすっかり幸せ気分に浸ってしまうナデシコ艦長だった。
結局、機関故障の原因はわかったものの、復旧には時間がかかるということでアキヅキに牽引をしてもらうことになった。
それまでの2時間半、ラピス・ラズリにささやかながら大切な成長の一ページが書き加えられることになるが、それはまた別の物語である。
Ⅴ
「うわー、お星様がいっぱい」
再出発後、艦橋の窓から宇宙の大海原を眺める少女はその圧倒的な真空世界に感嘆の声を上げた。紅く瞬く名も無き星、青白く光るガス状惑星、強く、時にはぼんやりと輝き続ける星々が織り成す幻想的な光の大河。
それらを一つ一つ掴み取るかのように、ラピスは目を輝かせながら移り変わる銀河の横顔に見入っていた。その表情は年相応の「少女」というのにふさわしく無邪気であり、ほんの数時間前まで頑固に閉じこもっていたとは思えない笑顔も見せていた。
「どう、ラピス? ずっと部屋にいるより楽しいだろう」
傍らにいるテンカワ・アキトが優しく語りかけると、少女は満面の笑顔で「うん」と大きくうなずいた。彼女がネルガルの教育機関にいたときとは全く違う環境と世界が広がっていたのだから……
「ルリちゃんより感情が豊かかな? イネスさんの話だと記憶障害の影響らしいけれど、よい方向に作用したのなら幸いだな」
アキトは、少女の横顔を一瞥して窓の外を見た。宇宙は変わらない。空と同じだ。どこまでも続く光と闇の共演。物言わぬ漆黒の空間に心を癒されてしまうのはなぜなのだろうか? すべての物語の始まった舞台だからだろうか、宇宙という未知へ憧れ続けた想いが世代を越えて受け継がれ、それが「テンカワ・アキト」という一人の小さな存在の青年にも宿っているからだろうか?
希望、憧れ、畏れ、未来。宇宙のかなたは、はるかな時代を経ても人類とそれを見つめる存在にとって広大で変わらない聖域であり続けるのならば、変わらなければならない個人もある。
テンカワ・アキトは変わらなければならなかった。彼自身が痛烈に感じたことであり、大切に想う人たちを守るために絶対に成長しなければならないのだ。より強く、より強く、誰にも負けないほど強く!
なぜなら、彼は夢を見てしまったから。無数のエネルギービームが飛び交う最中にあるナデシコに一筋の光の刃が突き刺さる夢を見てしまったのだ。
「ただの夢」
だとは考えたくなかった。あまりにもリアルであまりにも恐ろしすぎる光景。なす術もなく、一瞬のうちに火球と化すナデシコを呆然と見ていることしかできなかったテンカワ・アキト。
これは「警告」だとアキトは考えた。弱い自分自身が見せた、今のままだと起こりえる現実を深層世界が未来視したのだと。それを回避するために「出来ることをやれ」と教えてくれたのだと。
◆◆◆
「アキト、どうしたの?」
はっとした青年は、心配そうに彼を見上げる一人の少女に気がついた。彼女は青年の手をしっかり握っており、その温もりが乱れた心を落ち着かせてくれた。
「ごめんね、ラピス。なんでもないよ。とってもキレイな宇宙にぼーっとしちゃったんだ」
もちろん、とっさの台詞だがアキトは反省した。ラピスは鋭い。彼女に感づかれてしまうような顔をしていたとは……周りを不安がらせてどうするんだ! 以前、アカツキさんに言われたっけ「君はわかりやすい人間だね」と……
感情が表に出やすいということだろうか?
いずれにせよ、これから成長して強くなるというなら、ゆるい精神面をもっとしっかりしないといけない。周りの人を不安がらせるようじゃ、とてもじゃないけど「大切な人を守る」なんていってる場合じゃないよ。
「まだまだ反省点は多いな」
アキトは振り返った。一番上のメインデッキには艦長のミスマル・ユリカ、副長席にはアオイ・ジュン、ゴート・ホーリーが少し後方の戦闘指揮席に座り、企業戦士のような格好でプロスペクターが前方を見ながら直立している。下方のデッキには操舵士のハルカ・ミナト、中央にメインオペレーターのホシノ・ルリ、そして左隣に通信士のメグミ・レイナード。エステバリスパイロットの女性カルテットはアキトたちと同じく左舷の窓付近に集まってなにやら談笑していた。エリナとアカツキは席を外していて姿は見えなかった。
「ここも変わらないな」
地球を出発してからはや2年。失った人もいるが概(おおむ)ね艦橋の光景は変わらなかった。ひょんな縁からナデシコに搭乗してからずっと続く日常。
「ここは変わらなくていい、いつまでも変わらない日々の中で過ごしていたい心安らぐ空間と仲間たちであってほしい」
アキトは心からそう思った。はるか未来にいるからこそ、ここが彼らの故郷になっているからこそ変わらない仲間との必要な時間……
「んっ?」
ふとアキトがラピスのほうを見ると彼女は誰かに向かって手を振っている。その視線の先をたどると、ラピスと同じ境遇の琥珀色の瞳を持つ少女に行き着いた。
「ちょっとルリルリ、ラピスちゃんが手を振っているわよ。お姉さんとして応えてあげなくていいの?」
ミナトが小さい声でルリに促すと、オペレーターの少女は少し迷ったような顔をし、視線をやや外し気味にしてぎこちなく右手を振った。
「ちょっ、恥ずかしがっちゃって。かわいすぎよ、ルリルリ!」
ミナトの笑い声がルリの横顔に吸い込まれていく。それは艦橋中に連鎖したが、少しも意地の悪くない温かな笑いだった。
Ⅵ
ナデシコ艦内食堂
夕食を終えたイツキ・カザマはお気に入りの紅茶を飲みながら一息ついていた。事前の予定ではすでに基地に到着しているはずだが、機関故障のために到着は深夜になることが確実になっていた。
「小官のほうで基地に通信文を送っておきました。到着は標準時で24時を回りそうですが、あせらず確実にすすんで欲しいとの基地司令官閣下よりの返信がありました」
そうユリカに報告したムネタケ少佐は到着予定時刻も算定ずみという手際のよさだった。
「まさか、ムネタケ提督に再びお会いするなんて」
そのイツキの感想は幻想が紛れ込んだ認識のいたずらではあったが、既視感(デジャヴ)と故人に対する記憶が強く印象に残っていたためにこぼれ出たなつかしさの表現でもあっただろう。それもそのはずで、イツキはムネタケがナデシコの乗艦提督となったときエステバリスの補充パイロットとして一緒に着任したのだった。軍人として育った彼女にとって共に着任したムネタケがナデシコ乗員に評判がよろしくないとはいえ、上官の命令は絶対だった。時にイツキに無理難題を押し付けたムネタケだったが、彼の過去を多少なりとも知っていた彼女の態度は「中立」で終始した。
着任前、パイロット養成学校を首席で卒業し、新設されたエステバリスのエース部隊に配属予定だった18歳の才女は民間企業が建造し、当時すでにでたらめな活躍をしていた最新鋭艦ナデシコへの転属命令を受けていた。
「もちろん、謹んでお受けいたします」
イツキは即答した。上層部の命令だけではない。地球連合の一員として謎の機械兵器木星蜥蜴と戦う決意をしていた彼女にとって、常に最前線にあって多大な戦果を上げてきたナデシコへの転属は願ったりかなったりだった。
その理由は他にもあった。イツキの家族や友人も木星蜥蜴の攻撃に巻き込まれて亡くなったりケガをする者が多く存在した。彼女はそんな現実を打開すべく、軍人生命をかけてナデシコに着任したのだった。
しかし、着任早々、イツキは実戦の恐怖を味合うことになる。ジンタイプの巨大メカの迎撃に出たイツキ・カザマは、まさに間一髪で「死」を回避した。ボソンジャンプを繰り返してエステバリスを翻弄する木星のロボットに対し、イツキは相手に密着することでジャンプをされても攻撃ができると相手に張り付いたのだが……
彼女は知らされていなかった。いや、通常の人間がボソンジャンプに耐えられないことを知らなかったのだ。リョーコがとっさの判断でイツキのエステバリスに体当たりしなければ彼女は無残な形でこの世から消滅していたであろう。
イツキにとって背筋の凍りつく出来事だった。たった一日でこの世とさよならすることになりかけるなんて……
イツキは、しばらくそのときの恐怖がよみがえるときがあり、その都度に他のパイロットたちに迷惑をかけたものだが、今こうして生きていられるのも、その恐怖を仲間たちに励まされながら克服できたからだった。
あれからさらに8ヶ月あまりが過ぎ、イツキは最後までナデシコのエステバリスパイロットとして幾多の戦いに身を投じ、そして生き残った。
◆◆◆
イツキは紅茶を一口すすった。ナデシコに着任して以来、食後の紅茶は彼女の楽しみの一つになった。これもホウメイのこだわりのおかげだろう。彼女は宇宙戦艦という兵器の中にいながら日々の楽しみに困らない日常を過ごしていけるのだ。
「おかわりいかがですか?」
ややぎこちないが、天使のような微笑でイツキに話かけた少女がいた。白いエプロンと三角巾を身につけた(なぜか服がメイドっぽい)その少女はトレイを両手に抱いて楽しげな笑顔を向けている。
「そうね、いただこうかしら。お願いね、ラピスちゃん」
イツキが差し出されたトレイにティーカップを乗せると、ラピス・ラズリはうれしそうに弾んだ足取りでカウンターへと歩いていった。
「変わらないものがあれば変わるものもあるのね」
平穏な光景に新たにはめ込まれた一片のパズル。その空間にほのぼのとした陽光をあてた一人の少女。
ラピス・ラズリは食堂を手伝っていた。

イツキがカウンターに視線を移すと、ちょうどラピスが新しいティーカップをサユリから受け取っているところだった。少し奥では久しぶりに厨房に姿を現したテンカワ・アキトが今までの分を取り戻すように忙しく調理に励んでいた。
「お待たせしました。紅茶をお持ちしました」
ラピスが可愛いい声で丁寧にティーカップをイツキの前に置いた。
「ありがとう。お手伝いとてもえらいわね。おねえさん感心しちゃった」
にこっとラピスは誇らしげに微笑した。イツキに向ける笑顔は純真そのものであり、少女がホシノ・ルリと同じく特殊なIFS処理を施されたマシンチャイルドだということを全く感じさせないが……
「ラピスちゃん、楽しい?」
うん、とラピスはうなずいてお辞儀をし、トコトコと他のテーブルへ歩いていった。
「ルリちゃんとはずいぶん性格が違うみたいだけれど?」
イツキが感じたことを、少し前まで同席していたイネス・フレサンジュも口にしていた。
「あの子、あんなに明るかったかしら?」
ラピスの教育も担当していたはずの科学者としては無責任な発言だが、金髪の女性が不思議がるほど少女は変わっていたようなのだ。事実、目覚めてから数日間、少女は全く姿を現さず、ほとんどテンカワ・アキトの部屋に閉じこもっていた。
イネスの話だとユキナもずいぶん手を焼いたらしい。差し入れをもってアキトの部屋を訪れた艦長とは一戦交えたということだった。
「テンカワさんも大変ね。けれど、何が彼女を変えたのかしら?」
イツキはその過程を考えたがどうにもイメージが湧かない。
しかし、テンカワ・アキトがラピス・ラズリを部屋から連れ出して今までの数時間、少女の心を開かせる何かがあったのだと確信できた。
──艦内時計時間20時00分──
ざわっと食堂が震えた。艦内TVのスイッチが入ると、どやどやとその周りに人だかりができる。ラピスが不思議そうにTVを覗き込むと自然と一番前の席が少女専用になり、クルーたちが笑顔で席を勧めた。
イツキもティ-カップを持って立ち上がった。
「新なぜなにナデシコ・同盟編」の第2回放送が始まったのだった。
Ⅶ
──標準暦10月4日、23時51分──
「識別コード確認。閣下、駆逐艦アキヅキと特務戦艦ナデシコを確認いたしました」
「よろしい。待機中の駆逐艦ベルテンⅡに連絡、周辺宙域の安全を確認後、発光信号にて2艦を誘導せよと」
「了解いたしました」
通信オペレーターがマクスウェル准将の指示を基地所属の駆逐艦に伝えるべく、すばやくコンソールを操作する。僚艦から送られてくるアキヅキとナデシコの映像をスクリーン越しに見ながら巨漢の基地司令官は内心でホッと胸をなでおろした。
「ふう、どうやら無事に到着しそうだな」
途中、アキヅキからナデシコが機関トラブルを起こしたと通信が入ったとき、マクスウェルは多少なりとも慌てたが、大事に至らず予定時間より遅くなるが基地に入港できると聞いて安堵したものだった。
なぜなら、マクスウェルは歴史の証人を迎えるのだ。しかも1400年前の地球人類と実在したかもしれない「戦艦ナデシコ」という失われたテクノロジーによって建造された至極の戦艦を!
マクスウェルは正直、通信では肯定したものの、まだ完全には信じられないでいた。ここ数日、あれは性質の悪い「幻」であり、気がつけばすべてに目が覚めているのではないだろうか。自分はきっとどこかでペテンにかけられ、ひと時の夢を見ているのではないだろうかと。いつか夢は覚めてしまうものなのだと……
「准将、第2ドックへの受け入れ体制、すべて完了したとの報告が入りました。また、アキヅキ、ナデシコともベルテンⅡの誘導にしたがってアステロイド帯に入りました」
オペレーターの声で我に返った基地司令官は、二瞬遅れて指示をした。
「ナデシコ艦長と話がしたい。通信を送って欲しい。まずいかな?」
「いえ、問題ありません。ただちに回線を開きます」
メインスクリーンに再び視線を向けたマクスウェルの瞳には、小惑星帯の中を順調に進んでくるナデシコの姿が大きくはっきりと映っていた。
幻ではなかった。オペレーターも認識しているのだ。マクスウェルの網膜には白と赤の配色がなされた双胴型の艦艇が確実に存在していた。彼の鼓動は高鳴った。
「閣下、通信開きます」
「うむ」
直後、通信スクリーンに待ち焦がれた「彼女」が映ったのだった。
◆◆◆
アスターテ星域にある比較的中規模の小惑星帯の手前でベルテンⅡの出迎えを受けたアキヅキとナデシコは、その誘導にしたがって徐々に奥のほうへと慎重に航行を続けた。
「うーん、なんか小惑星の中は気分がよくないわね」
ミナトが縁起が悪そうにつぶやくと、艦橋内からもいくつか賛同の声が返ってくる。その中の一人、スバル・リョーコが窓から外を眺めながら言った。
「まあ、仕方ないだろう。さすがは非公式の基地だけあるじゃん。たぶん、基地そのものが小惑星だぜ」
まさにその通りだった。
「だってねえ、そうじゃないと非公式の意味がないもんね」
と、ヒカルがさりげなく皮肉ったが、当然ながら基地側には聞こえていないので、基地司令官は名誉復活の反論はできない。ヒカルの突っ込みにあわせてマキ・イズミがなにやらダジャレをつぶやいていたが、とりあえず全員が左に受け流す。
そのとき、先行するベルテンⅡが発光信号を前方に送ると、11時方向にある直径が数キロはあろうかという小惑星からも同様の合図が返ってきた。
「あれがハーミット・パープル基地のようですな」
プロスペクターが確認するようにつぶやくと、指揮卓の前に優美に立つ艦長はだまってうなずいた。彼女は徐々に大きくなる基地を大きな瞳に映しながら胸中でささやかな葛藤を行っていた。ようやくここまで来れた。まずはナデシコを修理して、その間に情報を集めて原因がなんなのか考察して、終わったらボソンジャンプを試してみて、成功すれば元に時代に戻って──もしだめならみんなと協議して、それから……
ユリカの思考を断ち切ったのは一本の通信だった。開かれた通信スクリーンに映っていたのは、あいかわらずクマのような巨漢の同盟軍人だった。
「小官はハーミット・パープル基地司令官マクスウェル准将です。命令は統合作戦本部より受け取っています。特務戦艦ナデシコと乗員の方たちを心より歓迎いたします。ようこそ基地へ」
「ありがとうございます。特務戦艦艦長ミスマル・ユリカと申します。しばらく基地にお世話になりますが、どうぞよろしくお願いいたします」
事前の協議に沿った挨拶が交わされ、双方の敬礼が終わると一旦通信は切られる。マクスウェルとすでに面識のあるナデシコのクルーの反応は落ち着いたものだったが、准将とちがって初めてユリカを見た基地司令室のオペレーターたちの心は浮き上がりっぱなしだった。
「こらっ、気を引き締めぬか。見惚れて事故など起こしたらかっこ悪すぎるぞ」
マクスウェルの「クマの咆哮」に一喝され、緩んでいた司令室はいつもの勤勉さを取り戻す。彼も半分は自分に向けた言葉だった。
──標準暦10月5日、24時12分──
誘導ビームに牽引されて基地へと進むナデシコは、一緒に入港するはずだったアキヅキからの意外な通信を受け取っていた。
「えっ、このままハイネセンへ戻るのですか?」
ユリカがたずねると、アキヅキ艦長のムネタケ少佐は通信スクリーンの向こうから理由を口にした。
「今から全力で向かえば本隊と合流できます。いや、申し訳ありません。実は部下が早く家族や恋人に会いたいというものでして──かくいう小官も同じ気持ちです。ナデシコを無事に基地に送りましたので任務は完了しました。われわれ軍人にとって家族や恋人と過ごすことは、戦いの後、何者にも変えがたい心休まる時間でもあります」
ムネタケは微笑んだ。ユリカたちの知っている「彼」とはやはりちがう性質の穏やかさ。
「ムネタケ少佐、お気持ちお察しいたします。私たちも遠く故郷を離れ、今ここに居ります。私たちはもう大丈夫です。どうか一日も早くご帰還なさり、大切な方たちを安心させてください。ここまで本当にありがとうございました。どうかお気をつけて」
「ありがとうございます。短い間でしたが、特務部隊の皆さんと交流できたことを嬉しく思います。どうか御壮健でいてください。いずれハイネセンなりで再会できることを心より願っております」
ムネタケは敬礼した。ユリカも倣った。わずか数日間だけの交流だったが、ムネタケ少佐にかぎらずアキヅキの乗員たちはナデシコの乗員と等しく同じ心を持っていた。時が移り処が変われど、人の営みになんら変わることがないように、はるかに時が流れようと人の心もまた変わらないのだと。
だからこそ、大切なものを共有できたムネタケ少佐たちアキヅキ乗員のささやかな幸福と生存を心から願わずにはいられなかった。
数ヵ月後、ユリカたちは少し違った形で新たな「なつかしき人」と出会うことになる。そして、ナデシコに関わった幾人かの運命も分岐点を迎えるのであった。
──宇宙暦795年帝国暦486年、標準暦10月5日──
ナデシコ艦内時計時間24時31分
ナデシコ艦内時計時間24時31分
はるか過去より遠い未来? の悠久の宇宙に跳躍した戦艦ナデシコは、一つの戦いと二つの出会いを経験し、ついにハーミット・パープル基地に入港を果たした。
……TO BE CONTINUED
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
あとがき
みなさん、第二章後編をお届けいたします。
まだ先は長いですねー、外伝の中だしw
今回の後編でナデシコは基地に入港しました。その間のお話になります。意外な人を登場させましたが、みなさんはどう思われたでしょうか?
しばらく戦いからは外れていますが、まあ、状況的に仕方がありません。御勘弁を(汗)
前回の(中編)では、挿絵にオーベルシュタインとラピスを描いたのですが、その落差に笑ってしまいました。今回も落差のある挿絵となっていますw
今回も何か感じていただければ幸いです。
御意見、御感想もお待ちいたしております。
では、三章でお会いしましょう。
2008年10月9日 ──涼──
改訂にあたり、誤字や脱字、一部追記を行いました。
2008年11月16日 ──涼──
読みにくい段落差を解消し、一部修正を行いました
2010年1月29日 ──涼──
☆☆☆☆☆☆☆☆☆メッセージコーナー☆☆☆☆☆☆☆☆☆
前回もメッセージをいただきました。いや、遅くなってしまうのが申し訳ないです。
以下、返信とさせていただきます。ありがとうございました。
◆◆2008年9月7日◆◆
◇◇12時36分◇◇
「御回答して下さりありがとう御座います。ところで、①~⑤までの回答を読んで今更ながら気がつきました。TV最終回後の方がアフターとクロス、どちらで書くにしても新しいストーリーを創り出す余地がまだ充分にある事にです。ですから、完結後に新しくナデシコSSを書くときは、手前勝手なリクエストで申し訳ありませんが、最終回後でお願い致します。それでは、次回も楽しみにしております」
>>>>今回もメッセージをありがとうございます。楽しみにしていただけるとは光栄です。
TV本編のストーリーを大切にされているようですね。それもまた作品を愛するということだと思います。
なるほど、余地がありますか。まったく異なったストーリー展開も可能かもしれませんね。ただし、劇場版の背景が多くのファンに支持されているようですし、銀英伝で「跳躍」してしまうネタは使ってしまったので、さて次があったら悩みますね。できれば違う視点からの「ナデシコ作品」を書きたいと思っています。
◇◇22時31分◇◇
「同じ戦艦なのにナデシコ作品と銀英作品の戦艦の大きさは三倍近くはなれているんダヨナ。正直、ナデシコがそんなに活躍出来るとは思えないな。エステバリスの武装とか貧弱すぎて船落とせないだろうし。TVで木連の船落としてるけど実際アレだけじゃ撃沈できんだろ」
>>>メッセージをありがとうございます。
この件に関しましては、以前より他にもメッセーをいただいていますが、どうやって作者が乗り切るのか、ぜひご覧になっていてください。けっこう簡単に解決できますよ。じゃっかん、ノリで行くかもしれませんがw
◆◆9月8日◆◆
◇◇16時36分~16時47分◇◇
今回もまた、楽しく読まさせていただきました。「義眼」が登場しましたか。さて、彼がナデシコに対してどのように動くのか楽しみですね。ところで、ラピスが出てきましたが、このラピスはどの「時代」、若しくは何処の「世界」のラピスなのですか?
>>>メッセージを毎回ありがとうございます。
オーベルシュタインがどこまでナデシコに迫れるのか、なかなか見ものです。彼の行動がどう銀英伝世界で作用するのか、わかりませんw
このラピスは、ネルガル時代のラピスと劇場版ラピスの間のラピスって感じです。だから設定的にはオリジナルですね。
ラピスの登場は一章の後編を書きおわる直前まで悩んでいました。基本的に二次小説では劇場版設定のラピスの登場がほとんどなので、それから外れるラピス・ラズリを登場させるには、なにかと設定やらファン心理やらがむずかしかな?と考えていました。
とある方に相談したところ
「出しちゃってください」
というご意見をいただきましたので、ラピスを登場させましたw ルリとは違うラピス像っていうのがありますので、まあ、愛される存在になればいいのですがね。
「話は変わりますが、ボソンジャンプの元ネタというかヒントはE・R・バローズの「火星のプリンセス」なんですかね?久しぶりに本棚から引っ張り出して読んでいたら、地球に居たはずの主人公が火星に跳んでいく場面があったので、なんとなくそう思ってしまいました。長文になりましたが、次回も首を長くしてお待ちしていますので頑張ってください。」
>>>なるほど。ボソンジャンプの元ネタですか。どこかでそれっぽい記述を見たような幻のような……
古典SFも読まれているようですね。逆に今のSFより新鮮だったりする物語もあります。私もSF作品は好きなので、スターウォーズやインデ・ペンデンス・デイ、スタートレックなどを読んでいます。中でもエドモント・ハミルトンの「スターウルフシリーズ」はなかなか面白かったです。どちらかというとアクションSFなのですが、10倍の重力の惑星で育った主人公はあるアニメの主人公と重なったり、人類以外の宇宙人の設定とか、さすがSF作家だと感じました。これもそのうち映像化して欲しいですね。
そういう意味では、スターウォーズシリーズの中でティモシイ・ザーンの「帝国の後継者」だけは映像化して欲しいと願っています。
◆◆9月9日◆◆
◇0時28分◇
「絶対正論忠臣者オーベルシュタイン、えげつないけど解ってて使えば能吏」
>>>>メッセージをありがとうございます。オペの正論にはラインハルトもたじたじの観がありました。ですが、正論だけが世の中を動かすわけじゃないんですよね。なぜオペはそこまでこだわったのでしょうか?
オーベルシュタインはオペであり続けるでしょう。
◇◇18時06分◇◇
「ペテン師の「全艦、逃げろ」という号令はいつ頃になりますか」
>>>メッセージをありがとうございます。どうもお待ちいただいているようでして、作者も恐縮です。彼の名台詞ですね。好きな台詞の一つです。なんというか、まだアスターテに突入していませんので、もうちょい先かとw
えーと、予定では四章くらいから物語がだいぶ動きます。名台詞連発の章までもうすこしお待ちください。
以上です。メッセージをありがとうございます。
2008年10月9日 ──涼──
☆☆☆☆☆☆☆☆☆メッセージコーナー☆☆☆☆☆☆☆☆☆
◎◎◎◎◎◎◎なにそれ?ナデシコのコーナー(その④)◎◎◎◎◎◎◎◎
はーい、みなさんお久しぶりね。イネス・フレサンジュです。ようやく状況も落ち着いたので私の出番というわけです。
今回のなにそれ? は、私たちが恐ろしい目に遭ったヴァンフリート星域で行われた会戦について御説明します。ウランフ提督から提供された軍事資料の中に混ざっていたものなんだけど、その会戦規模にみんな眼を丸くしていたわね。
では、説明しましょう。ヴァンフリート星域の会戦は宇宙暦794年帝国暦485年、3月21日から始まり、なんと両軍撤退まで40日を要するものになったそうよ。
会戦そのもののきっかけは、帝国軍の侵攻に対し、同盟軍が迎撃したということね。
参加した艦艇は帝国軍32700隻、将兵の数は実に約407万人。同盟軍が艦艇28900隻、将兵約336万人だそうよ。
なんというか、スケールが違っているわね。思わず見てみたいと考えるのは私だけではなさそうね。
さて、会戦の進行ですが、どうやら結論的には決着がつかなかったようね。私たちが体験したようにヴァンフリートは惑星やら衛星やらがたくさんひしめく狭い宙域です。そこに何万隻もの艦艇が集まって、自由に戦いができるはずがないものね。結果、両軍の艦隊は散在する諸惑星に散らばって戦闘を行なう羽目になり、どちらも決定打を出せない状態で最終的には撤退したということね。
死者の数は100万人に達したそうだけど、この数も大きすぎて私にはぴんと来ないわね。
私って冷酷かしら?
もう、長い間「痛みわけ」の状態が続いているみたいだけど、まさにヴァンフリートの会戦は両勢力の前に進めない実情を反映したと言えるでしょうね。ウランフ提督はこの会戦には参加されていなかったそうよ。なんというか、上手くいかないものなのね。
今回は以上です。それでは次回にまた会いましょう。
イネス・フレサンジュがお伝えしました。
◎◎◎◎◎◎◎なにそれ?ナデシコのコーナー(その④)おわり◎◎◎◎◎◎◎◎
<<前話 目次 次話>>